INFORMATION
SE構法について①
2016/03/09
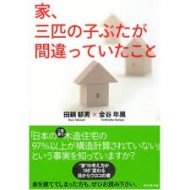
「家、三匹の子ぶたが間違っていたこと」
著者 田鎖 郁男、金谷 年展
発行所 ダイヤモンド社
2007年11月8日 第1刷発行
これまで3回にわけ、こちらの本の中から
①木造住宅は日本に適しています。
②強い家をつくるためには、構造計算!
③耐震性に優れたSE構法、その生い立ち
といった内容のお話をご紹介してきました。
そして今回は
SE構法の仕組み、構造システムについてです。
それではまず、
建物の代表的な構造ですが、
【木造】
木造軸組工法
→ 在来木造軸組工法
→ SE構法
木造枠組壁工法(2×4工法)
【鉄骨造】
【鉄筋コンクリート造】
【鉄骨鉄筋コンクリート造】
(この他に、木質系やコンクリート系などの種類をもつプレハブ工法があります。
日本では年間かなりの数のプレハブ住宅が建てられていますが割愛します。)
などがあります。
このうちの
木造の工法のひとつである、
木造枠組壁工法は
北米から導入され普及したた工法で
床・天井・4面の壁、の6面の木製パネル(面材)で
建物を支える、というもの。
このとき、パネルをはめ込む枠となる木材の断面のサイズが
2インチ×4インチのものを用いるものを、2×4工法と呼びます。
最近は2×6インチの枠組壁工法もあります。
これに対し、
木造軸組工法は、
木の柱と梁で建物の基本骨格をつくります。
このうち、
在来軸組工法(在来工法)と呼ばれるものは
日本の木造住宅の最も主流な工法で、
木の柱と梁に
斜め方向を支える筋交いをいれて建物を支えます。
(この筋交いや壁量の話は前々回の記事「構造計算について」を読んでください。)
それでは
SE構法の場合はどうでしょうか。
SE構法では
筋交いはつかいません。
代わりに
在来の筋交い壁の3.5枚分の強度をもつ
耐力壁をつかいます。
これにより、全体の壁の量をおさえることができます。
また、柱と梁の接合部ですが、
在来工法では
ほぞ・ほぞ穴をつくり組み立てることが基本となり、
さらに、金属のボルトやプレートで補強をします。
SE構法では
ほぞをつくることで、木材が断面欠損し
結果的に強度が落ちる、脆くなると考えるので、
ほぞ継ぎはしません。
代わりに
特殊なSE金物と、Sボルトを用いて接合します。
このように、柱と梁を強固に剛接合したものは、
「ラーメン構造」とよばれ、
鉄骨造や鉄筋コンクリート造で一般的なのですが、
SE構法は、
このラーメン構造を、木造建築で可能にしました。
(ちなみに「ラーメン」はドイツ語でRahmen「額縁」という意味)
ここまで、
SE構法の特徴である
耐力壁と、接合部分について説明しましたが、
もうひとつ、大きな特徴があります。
それは、
構造材として
無垢の木材はつかわず、集成材を用いることです。
長くなってしまいましたので、
家の骨格となるこの大事な構造材については
また次回にしようと思います!