INFORMATION
「家、三匹の子ぶたが間違っていたこと」構造計算とは
2016/02/17こんにちは。
しばらく間があいてしまいましたが
前々回の、木造住宅に関するお話しの続きです。
こちらの本、
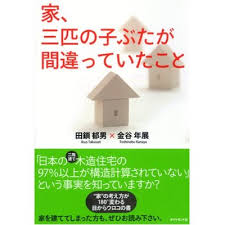
「家、三匹の子ぶたが間違っていたこと」を読んで
なるほど!!と思ったことを書いています。
前回は
日本では、
二番目のお兄さんの木の家が一番安全ですよ、
という内容でした。
今回は、
その安全な木の家をさらに安全にするための
構造計算
についてです。
構造計算とは
建物に使われる材の強度や
建物全体の重さ(積載荷重も含め)、
上下階のバランス、重さと硬さのバランス
そして、地震や台風で建物にどのように力が加わるのか、その強さはどのくらいなのか、
その力に耐えられるのか、
などをすべて調べ、計算し、
安全な家のための、科学的な数値を出すことです。
しかし、この構造計算、
日本の法律において
延べ床面積500㎡、二階建て以下の
一般的な木造住宅では
義務付けられていません。
ではどうしているかというと、
建築基準法に基づく、耐震基準の「壁量規定」
をクリアしていればよいのです。
壁量規定では
床面積から、必要な壁量と筋交いを割り出します。
そして、
建設時にその数の壁と筋交いを使えばよいのです。
これは、
左右対称、上下が同じ間取りの建物には効果が期待できるようです。
しかし、
吹き抜けやら、一体型バルコニーやら、
はたまた
グランドピアノを置いたり書庫をつくったり、、
特別な重さがかかることなどは
考慮されないので、
そういった場合に本当に耐えられるのでしょうか?
また、
梁の本数や大きさは調べませんし、
力の伝わり方や床の強度は調べないので、
筋交いも、どこに入れるかまでは
決められていません。
力学的な計算はされないのです。
実際、
日本で大地震が起き、家が倒壊するたびに
この規定の壁量というものは、そっと増やされてきたようです。
つまり、現在の規定の壁量をクリアしていても、
さらに大きい地震で崩れるかも!?ということでしょうか・・。
そもそも
なぜ構造計算をしないのでしょうか。
理由は3つ!
1、コスト
地震で家が壊れても罪には問われませんし、
損害保険も天災は免責されます。
つまり安全性を担保にすること自体、利益の損失!
そして単純に、
構造計算費用、地盤調査費用、
壁も規定より増えるので材料費も上がる・・などのコストアップ。
2、そもそも木材の強度がわからない
自然素材の無垢材は、強度が均一ではないのです。
3、はっきりさせないことで儲けを出す
「とにかく無垢材!天然志向!
集成材は使いません
大工の腕前に自信あります!」
などの宣伝文句の方が消費者の心に響くので
高い値段をつけられます。
さて、
そんな建築事情の中で
この本の著者のひとりである田鎖 郁男さんは
1996年に、エヌ・シー・エヌ(NCN)という会社を設立し
「SE構法」
という工法を用いて
すべての木造住宅が
構造計算のもとに建築されるように、と
活動されています。
次回はいよいよ、
この
SE構法についてです。
エヌ・シー・エヌ(NCN)のサイトはこちらからどうぞ。
最新のコラムにて、こちらの本の内容も載っています。
→ NCN

参照
「家、三匹の子ぶたが間違っていたこと」
著者 田鎖 郁男
金谷 年展
発行所 ダイヤモンド社
2007年11月8日 第1刷発行